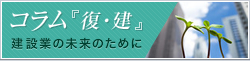2025/10/28
言葉は〝生き物〟
▼言葉はつくづく〝生き物〟だと痛感させられる。元来の意味から変化していく慣用句もあれば、まったく違う意味で日常的に使っている言葉もある。近年ではSNSの影響も大きい
▼文化庁が発表した2024年度の「国語に関する世論調査」でも、文字や語句、言葉の使い方が変化している実態が浮き彫りになった。言葉に敏感でなければならない新聞業に身を置く者としても、誤用や思い込みなどには十分気をつけたい
▼たとえば「にやける」は、元来の意味の「なよなよとしている」と答えた人が10・5%にとどまり、「薄笑いを浮かべている」が81・9%と多数を占めた。「役不足」は、元来の意味の「本人の力量に対して役目が軽すぎること」が45・1%だったのに対し、48・9%が「本人の力量に対して役目が重すぎること」と答えた
▼「潮時」は、元来の意味の「ちょうどいい時期」が41・9%に対し、46・7%が「ものごとの終わり」と回答。また「したり顔」は、元来の意味の「得意げな様子」が64・5%だったが、25・1%が「知ったかぶりをしている様子」と異なる理解をしていた
▼「御苦労様」は、現代では目上の人には使うべきでないとされることが多いが、調査では、下の立場の人に対して使うことも年々減少。24年度は14・9%にとどまり、この10年足らずで半減した。社会や組織内の上下関係が薄まったため、部下に対しても使われなくなった可能性が考えられる。一方で「お疲れ様」を使う人は全体の7割を超え、「ありがとう」を使う人も増加した
▼このほかSNSの利用の広がりで、短い言葉でのやり取りが増える「短文化」も進んでいる。「エモい」「ポチる」「映える」などなど。省略や略語を特徴とする若者言葉には、上の世代は筆者も含めなかなかついていけない
▼ただ、異なる意味で使っている言葉もその割合が多くなれば、必ずしも間違いとは言えなくなる。むしろ、どういう意味で使われているか、意思疎通を図る上でもより注意が必要になるだろう。