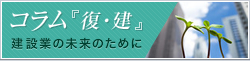2025/04/16
依然厳しい南海トラフ想定
▼この数字をどう受け止めればいいのか。一喜一憂せず、冷静にとらえて、最大限有効な対策を立てるべきとはわかっていても、どこまでそれができるのか。いよいよ日々の積み重ねが重要と言うほかはない
▼東海沖から九州沖を震源域とする南海トラフ地震の新たな被害想定が先月末に出された。死者数は最大で29万8000人、全壊・全焼失棟数が235万棟に上るとされた。前回2012~13年に公表された想定(32万3000人、238万6000棟)から微減にとどまり、政府の減災目標を大きく下回った
▼前回想定以降の防災対策に大きな効果がなかったとも考えられ、前回想定をもとに対策に力を注いできた自治体の戸惑いは依然大きなものだろう
▼南海トラフ沿いでは約100~150年の間隔で大地震が繰り返し起きており、前の大地震からすでに80年が経っている。30年以内の発生確率は80%程度とされ、あす発生してもおかしくない状況に、不安や危機感は募るばかりだ
▼今回の想定では、死者数29万8000人のほか、災害関連死が最大5万2000人とされた。能登半島地震などを参考にした推計で、被害規模が大きければさらにこれだけ被害が拡大するとするこの数字が示された意味は大きい
▼このほか、負傷者は95万2000人(前回62万3000人)、避難者1230万人(同950万人)、浸水(30㎝以上)11万5150ha(同8万7380ha)、経済被害202・3兆円(同237・2兆円)で、いずれも前回想定を大きく上回っている
▼想定される事態としては、いずれも最大時で停電2950万軒、断水3690万人、食糧不足1990万食、飲料水不足4370万リットル、孤立集落2700集落など、被害の甚大さは計り知れない
▼いずれにせよ、南海トラフ地震による被害は極めて広域に及び、過酷と言わざるを得ない。住民一人ひとりがこの想定を直視することが、少しでも被害を減らすことにつながる。今回の調査結果から目をそむけることはできない。