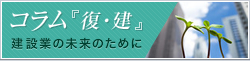2025/06/23
柳田国男と千葉
▼今年は日本民俗学の創始者、柳田国男(1875~1962)の生誕150年にあたり、その功績を振り返る企画展やシンポジウムなどが各地で開かれている。千葉県立中央博物館では「民俗学の父・柳田国男」と題する企画展が15日まで催された。柳田著作の初版本を蒐集した平野亥一(きいつ)コレクションを軸に、代表作『遠野物語』とつながりのある新出の書簡など約80点の史料が展示された
▼同展で思いのほか驚いたのが、柳田と千葉の縁の深さだ。その膨大な業績ゆえに、個人的にはそこに焦点を当ててみたことがなかったが、千葉との関わりが幼少期から長く続いていたことを知った
▼12歳のころ茨城県北相馬郡布川町(現在の利根町)に移り住んだ柳田は、幼少期を利根川のほとりで過ごし、兄の鼎(かなえ)宅の訪問や旅行でたびたび千葉を訪れた。農商務省の官僚時代に千葉県会議事堂で農事に関する講演を行うなど、民俗学の研究を始めてからも何度か講演に訪れている▼昭和16(1941)年5月には、印旛郡国語教育研究会の例会で講演するために遠山村(現在の成田市)を訪れ、遠山小学校で「方言の調査について」と題する講演を行っている
▼柳田が最後に公開講演を行ったのも千葉で、昭和35(1960)年5月、千葉市の青雲閣で房総民族会が主催した「柳田国男先生を囲む会」で講演し、翌日には布佐(現在の我孫子市)の松岡家へ兄・鼎の親族を訪ねている
▼昭和40(1907)年6月には、千葉県が文部省から交付された普通教育奨励費を利用した移動図書館(通俗巡回文庫)の開設にも、柳田や兄の鼎が尽力した。また、布佐の竹内神社に日露戦争時の旅順陥落を記念して建てられた石碑にも、柳田や鼎、弟の静雄の名が刻まれている
▼柳田は、明治26(1893)年2月に布川から対岸の布佐町に移り住んで医院を開業した鼎とのつながりもあって、千葉の地と縁が深かった。「手賀沼の蛸釣り」と称して弟の静雄にいたずらをして怒らせたなどの愉快なエピソードも残されている。