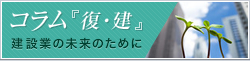2025/07/14
新紙幣発行から1年
新紙幣が発行されてから3日で1年を迎えた。20年ぶりの刷新で、紙幣の新たな顔ぶれとともに話題を集めたが、1年経ってみれば、普及率は3割程度にとどまり、前回2004年の改刷時と比べてペースが半減するなど、時代の急激な変化の影響も受けている
▼背景には、急速に進むキャッシュレス化による「現金離れ」や、超低金利時代に膨らんだ「たんす預金」の影響などがあるとみられる。市場に出回っている新紙幣は5月末時点で約50億枚で、流通総数に占める割合は28・8%。04年の改刷時には1年後の普及率が61・1%に及んでおり、当時と比べると切り替えのペースは大幅に遅くなっている
▼新紙幣の肖像は、1万円札が「資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一、5千円札が津田塾大学を創設した津田梅子、千円札が血清療法を確立した北里柴三郎。なかでも1万円札は、1984年に聖徳太子の後継に福沢諭吉が登場して以来、約40年ぶりの変更だった
▼とくに渋沢栄一は、1万円札の肖像に採用されたことで脚光を浴びた。研究者によれば、これまでも閉塞感のある時代に注目されてきた人物で、今回も正しい道筋としての渋沢が求められていると指摘する。現代にふさわしい人物として、その業績が再認識されたと言えるだろう
▼新紙幣では、立体的なホログラムの採用など偽造防止の技術も進化した。使いやすさも向上させ、金額の数字も大きくした。目の不自由な人が触って、新紙幣の金額を見分ける「識別マーク」は、券種ごとに異なる位置に配置した
▼とはいえ、普及率がなかなか上がらないのは、急速なキャッシュレス化の進行で致し方ない。筆者自身も現金決済の機会がここ数年でめっきり減った。経産省の調査では、クレジットカードや電子マネー、QRコードなどによるキャッシュレス決済額が個人消費に占める割合は、24年に42・8%と初めて4割を突破した。今後も現金が使われる機会は減っていくが、信頼性の高い現金自体は根強く残り続けるとの見方が強い。