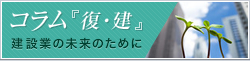2025/07/31
来年は「千葉開府900年」
▼来年6月1日の「千葉開府の日」まで1年を切った。2026年は開府から900年という大きな節目となり、「千葉開府900年」に関連するさまざまな記念事業が計画されている
▼千葉の始まりは平安時代後期に遡り、「千学集抜粋(せんがくしゅうばっすい)」の記述によれば、1126年6月1日に、桓武天皇のひ孫にあたる高望王(たかもちおう)(後の平高望)の子孫・千葉常重(つねしげ)が、現在の緑区大椎町から中央区亥鼻付近に本拠を移し、初めて「千葉」を名乗り、千葉のまちが成立したとされている
▼千葉氏は平安時代末期から戦国時代まで下総国(現在の千葉県北部など)を支配した関東の武士団で、千葉に本拠を移した常重の子・常胤(つねたね)は、源頼朝を助け、鎌倉幕府の創設に貢献した人物として知られる。頼朝の下で10年足らずのうちに全国各地に領地を獲得し、千葉一族の勢力を拡大し、一族「中興の祖」とも言われる。
▼千葉一族の家紋は、妙見に由来する月星紋(つきほしもん)や九曜紋(くようもん)で、この妙見を信仰することで一族の結束を強固なものにしていったと言われる。現在の千葉市の市章も、この月星紋と千葉市の「千」の字を組み合わせてデザインされている
▼「千葉」という名称の由来については、奈良時代にまで遡り、日本最古の和歌集『万葉集』に千葉郡の防人(さきもり)が詠んだ歌が残されており、「千葉」の地名が登場する。「千葉の野の 児手柏(このてかしわ)のほほまれど あやにかなしみ おきてたかきぬ」
▼「千葉の野の児手柏のように若くてあどけないけれど、なんともかわいくて手もふれずにやってきたことだ」という意味で、防人となった千葉の若者が故郷に残してきた初々しい女性を思って読んだもの。このことから、当時すでに「千葉」という地名があったことがわかり、この千葉という地名から、千葉常重も「千葉」を名乗ったことになる
▼千葉開府900年記念のキャッチコピーは「千の葉に 時を刻んで 900年」。動乱の時代に知力と胆力で未来を切り開いた先人らに倣い、私たちも千葉を、輝く未来へつなげていきたい。